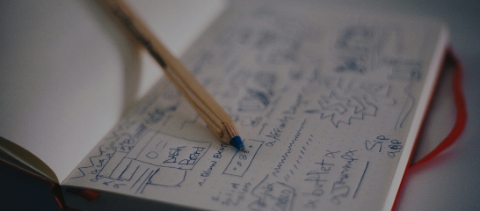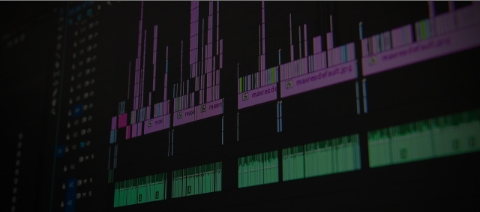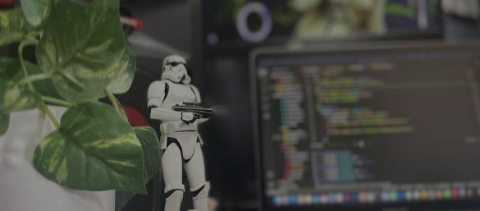お知らせ
【もう古い】今やっても効果の出ないマーケティング施策

1. マスメディア広告(テレビCM・新聞広告など)
かつての効果
かつてはテレビCMや新聞広告といったマスメディアへの大量出稿が、幅広い顧客にリーチする王道の手法でした。テレビや新聞が情報入手の主要手段だった時代には、これらの広告は一度に多くの人々の目に留まり、認知度向上や集客に直結していました。特にテレビCMはプライムタイムに流せば膨大な視聴者に訴求できるため、大企業のブランド構築には欠かせない施策だったのです。また、地方の小売店やサービス業者も新聞の折込チラシによって地域の顧客を効果的に呼び込むことができていました。
効果が薄れた理由
現在ではマスメディア広告の効果は大きく薄れています。
スマートフォンやSNSの普及により、特に若年層の多くがテレビや新聞をほとんど利用しなくなりました。その結果、テレビCMを放映しても視聴者は録画再生時にCMを飛ばしたり、そもそもNetflixなどオンデマンド配信に移行してリアルタイムで視聴しないため、広告を目にする機会が減少しています。
新聞に関しても購読者数の減少が顕著で、20〜40代へのリーチは極めて困難になり、折込チラシを入れてもターゲットに届きにくいのが実情です。
さらにマス広告は細かなターゲティングができず、広告費も高額になりがちなため、費用対効果の面でもデジタル広告に劣るようになりました。
具体例(業種ごと)
消費財メーカーなどは以前、テレビCMに巨額の予算を投下して新商品を周知していましたが、近年は若年層がテレビ離れしSNSやYouTubeに時間を割くため、テレビCMだけでは十分な効果を得られなくなっています。例えば飲料メーカーでは、テレビCMを流しても肝心の若者にリーチできず、YouTubeやInstagramでのキャンペーンに注力するケースが増えています。地域密着型のビジネスでも、かつては地元紙の広告や新聞折込チラシで集客できたものの、新聞購読者の高齢化と減少により反応率が低下しています。住宅リフォーム業者の例では、毎週チラシを配布しても反響が薄くなり、代わりにWebサイト経由の問い合わせ獲得にシフトする工務店も出てきました。
このように業種を問わず、マス媒体に依存した手法はかつてほどのリターンを期待しにくくなっています。
代替案
デジタルマーケティングへの転換が効果的な代替策です。限られた予算をテレビや紙媒体に投下するより、GoogleやSNSのオンライン広告に振り向ければ、狙った属性のユーザーにピンポイントでリーチできます。例えば、Google広告では地域や興味関心で絞り込んだ配信が可能であり、FacebookやInstagramの広告なら年齢層や趣味嗜好に合わせて露出を調整できます。
また、広告だけでなくコンテンツマーケティングへの投資も有効です。自社ブログやYouTubeで有益なコンテンツを発信し、SEOやSNSで拡散することで、従来マス広告に頼っていた分の認知を補完・拡大できます。さらに、マス広告的な一方向の訴求ではなく、インフルエンサーとの提携や口コミの促進によって双方向のコミュニケーションを図ることで、現代の消費者に響くブランド露出が可能になります。要するに、「万人に一斉に届ける」発想から**「必要としている人に届ける」戦略への見直し**が重要です。
2. テレマーケティング(電話営業)
かつての効果
「テレマーケティング(テレアポ)」とは、電話を使って見込み客に直接アプローチする手法のことです。インターネット以前の時代やデジタル化が進む前は、電話営業は新規顧客開拓の主力手段でした。営業担当者が電話でアポイントを取り付け、その後の訪問商談につなげるという流れは、多くの企業で新規獲得に有効に機能していました。
例えばB2B企業では、業種リストに片っ端から電話をかけることで短期間に多数の見込み客と接触でき、保険や証券などB2C向けでも夕食時に自宅へ電話して商品を案内すると一定の契約が取れる、といった具合に成果が出ていたのです。電話というパーソナルなチャネルを使うことでお客様の生の声を聞けるため、かつては直接的で即効性のあるマーケティング施策と考えられていました。
効果が薄れた理由
近年では電話営業の成功率は著しく低下しています。その最大の理由は、消費者側の行動変化です。スマートフォンの普及で見知らぬ番号は自動的にブロック・拒否されたり、着信があっても不審な電話には出ない人が増えました。また、特に若い世代ほど電話での勧誘を嫌う傾向が強く、企業からの唐突な電話に警戒心を抱きます。
こうした状況下では、かつては通用した大量電話によるアプローチもアポ取得率の低下に直面しています。
さらに、電子メールやSNSなど他のコミュニケーション手段が発達したことで、電話以外で情報収集ややり取りをしたい顧客が増え、電話自体の優先度が下がっています。結果として、多くの企業が電話営業に割くリソースに見合った成果が得られなくなり、効率の悪さが目立つようになりました。「電話すれば話を聞いてもらえる」という前提が崩れ、テレマーケティングは費用対効果の低い古い施策となりつつあるのです。
具体例(業種ごと)
B2B業界では、かつてITサービス企業が企業リストに電話をかけ、新システム導入の提案営業を行うのは一般的でした。しかし現在、多くの担当者は飛び込みの電話を敬遠し、メールで資料送付を求めたり、ウェブサイトから問い合わせする傾向にあります。とあるソフトウェア企業でも、かつては1日に100件テレアポしてアポイントを獲得していましたが、今では電話をかけても担当者不在や門前払いが増え、効率が落ちています。消費者向けサービスでも同様で、生命保険会社の例ではかつて電話勧誘で契約件数を伸ばしていましたが、近年は「お断り登録」されてしまい新規顧客につながりにくくなりました。さらに、通販会社が深夜にテレビ番組を見た視聴者に電話でセールスする手法も、録画視聴やネット通販の台頭で以前ほどの注文獲得に結び付いていません。このように、業種を問わず電話を使った一方通行の営業は敬遠されがちで、従来のような大量架電戦略は通用しなくなっています。
代替案
テレマーケティングに代わる現代的な新規開拓手法としては、インバウンドマーケティングへの転換が挙げられます。具体的には、電話で押しかけるのではなく、顧客から問い合わせをもらえる仕組みを作ることが重要です。例えば、自社サイトで有益なホワイトペーパー(専門資料)やウェビナー(オンラインセミナー)を提供し、興味を持った見込み客に登録・視聴してもらうことでリード(見込み客)情報を獲得できます。その上で、取得した連絡先に対してメールやSNSを通じてフォローアップし、必要に応じて温まったリードにのみ電話するようにすれば、無差別なテレアポよりも遥かに効率的です。また、営業プロセス自体もデジタル化が進んでおり、オンライン会議やチャットで商談が完結するケースも増えています。そのため、従来電話に充てていた労力をデジタルチャネルの整備に振り向けるべきでしょう。
例えば顧客層が集まるLinkedIn上で情報発信・コミュニティ形成を行い、関心を引いた相手にのみアプローチする、あるいはSNS広告で興味を持った人にだけ資料請求を促すなど、プッシュ型からプル型への戦略転換が効果を発揮します。要は、電話頼みの旧来手法を見直し、デジタル時代の顧客行動に合わせて**「問い合わせてもらう仕組み作り」**に注力することが求められます。
3. 購入リストへの一斉メール配信
かつての効果
電子メールが普及し始めた頃、メールマーケティングは低コストで大量の見込み客にアプローチできる革命的な手法でした。自社で顧客リストを持っていなくても、業者からメールアドレスのリストを購入し、一斉配信すれば新規リードの獲得が容易だと考えられていたのです。実際、かつては知らない会社からのメールでも受信者が目を通してくれる余地があり、競合するメールの数も今ほど多くありませんでした。例えば、あるソフトウェア企業は購入した1万件のアドレスに製品案内を送信し、一定数の問い合わせを得ることに成功していましたし、小売業でも割引クーポンのメールを大量送付して集客できていた時代がありました。当時は受信トレイへの到達さえすれば読んでもらえる可能性が高く、メール一斉配信は効果的な集客策としてもてはやされていたのです。
効果が薄れた理由
現在では、無差別なメール一斉配信の効果は大きく低下しています。まず、迷惑メールフィルターの高度化により、見込み客に送ったメールが受信箱に届く前にブロックされてしまうケースが増えました。特に購入リストを使った一斉送信はスパムと判定されやすく、こちらが送信しても相手の受信フォルダにすら入らないこともあります。
仮に届いたとしても、差出人に心当たりのないメールは開封されずに削除されたり、「迷惑メール報告」されてしまう可能性が高いでしょう。実際、受信者がスパムだと感じて報告すると、配信元ドメインの評価が下がりメールの到達率がさらに低下してしまいます。
こうなるとその企業からのメール全般が届きにくくなり、マーケティング効果は著しく損なわれてしまいます。
さらに、個人情報保護の観点からも無断でのメール配信は規制が強まっており(※日本でもオプトインが原則)、法律リスクやブランドイメージの毀損リスクも無視できません。こうした理由から、かつて有効だった大量メール配信は「届かない・読まれない・逆効果になり得る」施策へと変化し、もはや時代遅れとなりました。
具体例(業種ごと)
B2Bサービス企業の例では、展示会で名刺交換した相手や購入リストのメールアドレスに対し、一斉にセミナー案内を送る手法がとられていました。しかし最近では、こうした一括メールは多くがスパムフィルターにかかったり「不要な広告」として無視され、参加申し込みに結び付かないケースがほとんどです。結果として、せっかく開いたセミナーが定員割れになるなど効果不足が顕在化しています。小売・EC業界でも、以前は取得したメールアドレス宛に毎日のようにメルマガを送りつけ、セール品を宣伝するやり方が盛んでした。しかし今や、興味のない顧客には配信停止されるか開封すらされず、むしろ熱心に送りすぎたせいで「このブランドはしつこい」という悪印象を与えてしまうこともあります。飲食業のクーポン配布メールでも同様で、乱発すると顧客離れを招きかねないため慎重さが求められるようになりました。このように、業種を問わず相手の許可なく一方的に送り付けるメール施策は効果が出にくいのが現状です。
代替案
メールを活用しない方が良いという訳ではなく、手法のアップデートが必要です。まず重要なのは、メール配信の前提を「相手に許可を得て送る(オプトイン)」形に切り替えることです。
具体的には、自社サイトでニュースレター登録を募ったり、無料資料ダウンロードの際にメールアドレス提供の同意を得るなどして、自前で質の高いメールリストを構築することが肝要です。
そうして集めた見込み客には、一律に同じ内容を送りつけるのではなく、興味関心に応じてセグメント分けしパーソナライズしたメール配信を行います。例えば、過去の購買履歴から嗜好を分析し、その人に適した商品情報やコンテンツを送るようにすれば、開封率・クリック率ともに向上します。また、メールの内容も一方的な宣伝ではなく、読み手にとって有益な情報提供を心がけます。役立つノウハウや限定オファーなど、受信者が「読む価値がある」と感じるコンテンツを届けることでエンゲージメントを高めるのです。さらに、配信頻度にも配慮が必要で、送りすぎによる鬱陶しさを避けるため適切な間隔を保ちます。
これらの工夫により、メールは今でも顧客育成(リードナーチャリング)やリピート促進に高い効果を発揮するチャネルとなり得ます。要するに、旧来の大量一斉送信から、許可取得・セグメント化・コンテンツ重視の最新メールマーケティング戦略へとシフトすることが求められるでしょう。
4. 旧来型のSEO施策(検索エンジン対策)
かつての効果
SEO(検索エンジン最適化)は、かつて一部の「テクニック」によって容易に上位表示を実現できる時代がありました。具体的には、特定キーワードをページ中に大量に盛り込む、関連の薄い外部サイトからでもとにかく多数の被リンクを獲得する、文字を背景と同色にして隠しキーワードを仕込む…といった小手先の施策でも、昔の検索アルゴリズムでは効果が出ていたのです。
実際、2000年代前半には「●●市 美容室」といった地域名+業種キーワードを詰め込んだページが検索上位を独占したり、相互リンク集に登録するだけでドメインの評価が上がることもありました。当時のGoogleはまだ内容の真価を十分に判断できなかったため、こうしたSEOの裏技的手法が幅広い業種のサイトで横行し、それなりに成果を上げていたのです。
効果が薄れた理由
しかし現在では、これら旧来型のSEO手法は効果がないどころか逆効果になっています。検索エンジンのアルゴリズムが飛躍的に高度化し、「ユーザーにとって有益かどうか」を重視するようになったためです。
まず、キーワードの不自然な詰め込みは質の低いコンテンツと見なされ、かえって順位を下げる原因となります。。Googleは文章の文脈や自然な可読性を評価するようになったため、単に同じ単語を繰り返すページはスパム認定されてしまうのです。
また、大量の低品質な被リンクを設置するリンクスパムもペナルティの対象となりました。かつて有効だった「リンク集サイトへの登録」や無差別な相互リンクは、現在では検索順位を下げるリスクを伴います。同様に、隠しテキストや無関係なメタタグの羅列といった手法も今では検索エンジンに見破られてしまいます。要するに、以前は有効だったSEOテクニックの多くが今では通用せず、むしろ検索結果から除外される可能性すらあるのです
さらにユーザー側も目が肥えており、内容の薄いサイトはすぐ離脱してしまうため(直帰率が上がるため)、結果として検索エンジンからの評価も下がりやすくなります。こうした理由から、旧来的なSEO施策は現在ほとんど効果を期待できなくなっています。
具体例(業種ごと)
ECサイト業界では、以前は商品ページに関連キーワードを何十個も詰め込んだり、競合よりも多くの商品ページを機械的に生成することでトラフィックを稼ぐ手法が見られました。しかし現在、このようなページはGoogleに低評価を与えられ、検索上位に表示されにくくなっています。ローカルビジネスでも、例えば複数の都市名を羅列したページを作って各地域での検索流入を狙うケースがありましたが、現在では「価値のない薄いコンテンツ」と判断されてインデックスから外された例があります。さらにアフィリエイトサイトの分野でも、かつては自動生成記事や盗用コンテンツを量産して広告収入を得る手法が横行しましたが、今では検索アルゴリズムのアップデートでこうしたサイトは軒並み圏外に飛ばされています。「以前はこれで上手くいっていたのに、今は順位が上がらない」という声が各業界で聞かれるように、検索エンジンの進化に伴い旧式のSEOは業種を問わず効果ゼロになりつつあるのです。
代替案
現代のSEOでは、小手先の技ではなく質の高いコンテンツ作りとユーザーエクスペリエンスの向上が何より重要です。
検索エンジンはユーザーに価値ある情報を提供するサイトを評価するため、まずは自社サイト上にオリジナリティがありユーザーの課題解決に役立つコンテンツを用意しましょう。例えば、単に商品を羅列するのではなく、商品の選び方ガイドや活用方法の記事を掲載することでユーザーの滞在時間を延ばし、サイトの有益性を高めます。キーワードも依然重要ではありますが、不自然に詰め込むのではなく関連語や文脈を考慮しつつ自然に盛り込むことが大切です。また、技術面ではサイト表示速度の改善やモバイル対応などユーザビリティ向上施策もSEO評価に直結します。さらに、被リンクについては量より質が問われます。自演のリンクではなく、業界の権威あるサイトやユーザーから自然にシェア・言及されるようなコンテンツを作成することが最善の対策です。
例えば役立つ調査データやユニークなインフォグラフィックを公開すれば、他サイトやSNSで紹介され結果的に良質な被リンクが集まります。その際、業界のインフルエンサーに声をかけてコンテンツを共有してもらうのも効果的でしょう。
要するに、最新のSEOではユーザーに寄り添った有益な情報提供こそが王道であり、小手先の裏技に頼らず本質的なサイト価値を高める戦略へシフトする必要があります
5. SNS集客(オーガニック投稿中心)
かつての効果
FacebookやTwitter、InstagramといったSNSが台頭した当初、企業のオーガニック投稿(広告費をかけない通常投稿)だけでも驚くほどの集客効果を生み出しました。たとえば2010年代前半には、企業のFacebookページに投稿すればフォロワーの大半にリーチでき、新商品情報を投稿するだけで問い合わせや注文が殺到するといった成功例も珍しくありませんでした。SNSは口コミが伝播しやすく、一度バズれば爆発的な拡散が起きるため、中小企業でも上手く活用すればテレビCM以上のリーチを得る可能性があったのです。実際、「SNSで投稿すればお客さんが集まる」と言われ、多くの企業が競って公式アカウントを開設し、毎日のように情報発信を行っていました。こうしたSNS集客はかつて爆発的な効果をもたらし、広告費をかけずにファンを獲得できる画期的なマーケティング施策だったのです。
効果が薄れた理由
しかし現在では、SNSへのオーガニック投稿のみで顧客を集めるのは容易ではありません。その理由の一つは、プラットフォーム上の情報過多です。SNS利用者が増えた結果、タイムライン上には膨大な投稿が流れ、企業からの発信がユーザーの目に留まりにくくなりました。
また各SNSのアルゴリズム変更も大きな要因です。例えばFacebookでは年々アルゴリズムがアップデートされ、企業ページの投稿がフォロワーに表示されにくくなりました。フォロワー数を多く抱えていても、実際に投稿を見てもらえる割合(オーガニックリーチ率)が今では極めて低く抑えられているのです。さらに、SNS上の広告出稿が一般化し競争が激化したことで、有料広告に予算を割かない投稿の露出が相対的に減少しています。
例えばInstagramでは企業投稿より友人投稿や広告のほうが優先表示される傾向にあります。加えて、多くの企業がSNSに参入した結果、ユーザーのフィードはコンテンツ過多となり企業投稿へのエンゲージメント(いいねやシェア)が減少しています。こうした背景から、「SNSでただ発信するだけ」ではフォロワーすら十分にリーチできず、新規顧客の獲得には直結しにくくなってきました。実際、多くの企業が従来型の大量投稿戦略では十分な成果が出せないと感じており、SNS集客はかつてほどの威力を失いつつあります。
具体例(業種ごと)
飲食業界では、かつて新規開店する際にTwitterやFacebookで情報発信を続ければクチコミが広がり、オープン当日から行列ができるような事例もありました。しかし近年、同様にSNS発信してもフォロワーにすら情報が行き渡らず、思ったような集客につながらない店舗も出てきています。一方、アパレル業界ではInstagramでフォロワー数を伸ばしてブランド認知を図る戦略が一般的でしたが、アルゴリズムの変化や競合増加で投稿のリーチが低下し、フォロワー数が多くても売上につながらないケースが増えました。そのため有名ファッションブランドでさえ、新作告知にはインスタグラムの投稿だけでなく広告出稿やインフルエンサー起用を組み合わせるようになっています。B2B企業においても、以前はFacebookページで事例紹介を投稿すれば問い合わせが来たものの、今では投稿を見てもらえず反応が乏しいため、代わりにLinkedInで専門家グループに参加したり、ウェビナー開催をSNS広告で告知するなど工夫が必要になっています。このように、業種を問わずSNSのオーガニック運用だけで顧客を獲得するのは難しくなり、従来手法からの転換を迫られている状況です。
代替案
SNS自体が無効になったわけではなく、戦略の見直しと最新トレンドの取り入れが解決策となります。
まず、闇雲に投稿頻度を上げるのではなく、各投稿の質とターゲット適合性を高めることが重要です。具体的には、自社の商品やサービスに関心が高い層に刺さる内容を精選し、投稿ごとにメッセージを明確にする戦略です。量より質への転換により、限られたフォロワーへのリーチでも深いエンゲージメントを得ることができます。
また、SNSを他の集客チャネルと連携させることも効果的です。例えば、SNSの投稿から自社ウェブサイトの詳細記事やオンラインストアへの誘導を行い、そのサイト上でさらにメール登録や購入につなげる導線を作ります。
こうすることでSNS単体で完結せず、Web全体の集客フローの一部としてSNSを位置付けられます。加えて、新しいフォーマットやプラットフォームの活用も検討すべきでしょう。最近ではTikTokやYouTubeショートなどの短尺動画がトレンドであり、縦型動画コンテンツは高いエンゲージメントを生んでいます。静止画やテキスト中心から動画・ライブ配信へシフトすることで、新たな層の関心を引き付けられる可能性があります。さらに、予算が許すならSNS広告やインフルエンサーとの協業も取り入れると効果的です。オーガニック投稿だけでは届かない層に対しては、有料広告で確実にリーチし、興味を持ちそうなユーザーを自社アカウントに呼び込む戦略が有効です。また、ターゲット層に影響力のあるインフルエンサーに商品を紹介してもらうことで、従来の企業発信にはない信頼感と拡散力を得られます。最後に、SNS活用の最新トレンドとしてパーソナライズされた体験の提供も挙げられます。AIやマーケティングオートメーションを用いて、ユーザーの過去の行動に応じたコンテンツを配信したり、チャットボットで個別対応するなど、より個人に寄り添ったコミュニケーションを図ります。
総じて、SNS集客で成功するには従来の大量投稿・放置型ではなく、多角的かつ戦略的なアプローチで顧客とのエンゲージメントを高めることが鍵となるのです。
まとめ
- 旧来の施策を定期的に見直す重要性: 一度は有効だったマーケティング施策でも、消費者の行動変化や技術の進歩によって効果が薄れることがあります。効果の出ない手法にリソースを割き続けるのは非効率であり、競合に遅れを取る原因にもなりかねません。時代とともにブランドと顧客の接点は劇的に変化しているため、現在の戦略が「過去の成功体験の惰性」に陥っていないかを定期的に検証することが大切です。マーケティング担当者や事業主は、データやフィードバックをもとに施策の棚卸しを行い、時代遅れになったものは思い切って捨て去る勇気を持ちましょう。古い手法を見直すことで、人的・予算的リソースをより効果的な戦略に振り向けることができます。
- 最新のマーケティング戦略を取り入れる考え方: 現代の顧客はただ商品やサービスを提供されるだけでなく、エンターテイメント性やパーソナライズされた体験、利便性までも求めています。その期待に応えるには、マーケティング施策も最新のトレンドやテクノロジーを積極的に採用していく姿勢が必要です。例えばデータ分析に基づく精緻なターゲティング、コンテンツの質を高めるブランディング戦略、SNSや動画プラットフォームの活用、AIによる顧客体験の最適化など、新しい戦術を柔軟に試すことを恐れないでください。重要なのは、自社のターゲット顧客が今どこで何を求めているかを深く理解し、それに合ったチャネルとメッセージでアプローチすることです。マーケティングの基本原則(顧客視点に立つこと)は変わりませんが、その実践手段は刻一刻とアップデートされています。常に最新情報にアンテナを張り、効果検証しながら改善を続けることで、移り変わる市場環境に適応した効果的なマーケティング戦略を築いていくことができるでしょう。