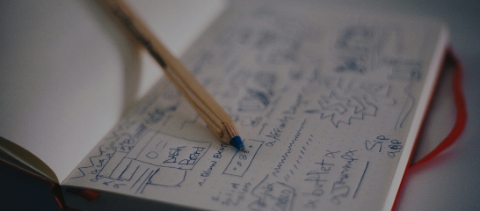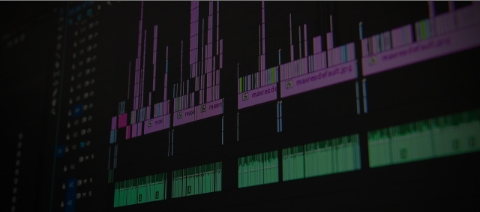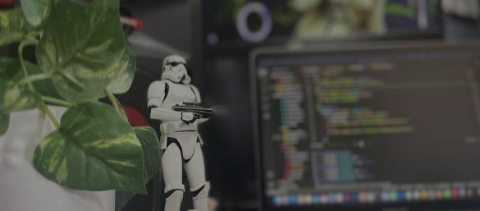お知らせ
それ間違ってない?企業が陥るSNSのNG運用5選
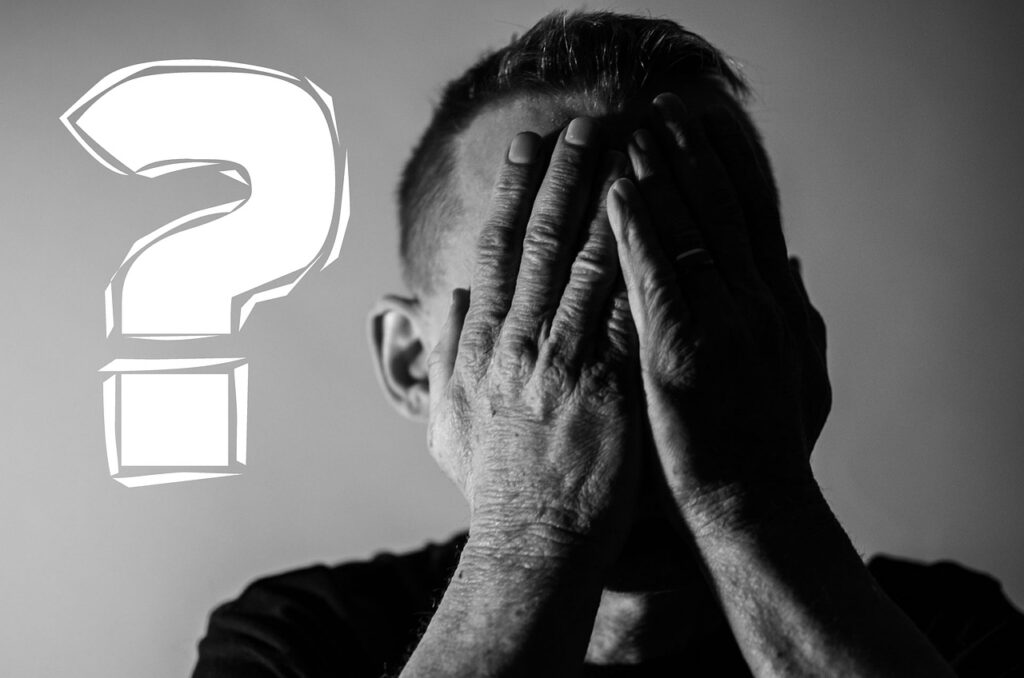
はじめに
現代では、スマートフォンとSNSの普及により、SNSマーケティングは企業にとって欠かせない手法となっています。
実際、日本ではほぼ全ての年代でSNS利用率が増加しており、40〜59歳でも80%以上、60歳以上でも半数以上がSNSを利用する時代です。
このように幅広い層にリーチできるSNSは、個人事業主から大企業までマーケティングに活用されています。しかし、「SNSを運用しているが成果につながらない」「何をどう発信すればよいか分からない」と悩む担当者も少なくありません。
そこで本記事では、SNS運用における誤ったやり方(NG行動)5選を紹介し、それぞれの詳細な解説と日本国内の成功事例から学ぶ改善策を述べます。正しいSNS運用のポイントを押さえ、ビジネスに活かしていきましょう。
日本でも幅広い世代が利用するSNSは、企業マーケティングの重要な舞台となっている(SNSのイメージ)
誤ったSNS運用5選
1. 投稿頻度が極端に少ない / 多すぎる
SNS投稿の頻度は多すぎても少なすぎても問題です。まず、投稿が少なすぎる場合、フォロワーのタイムライン上に自社の情報がほとんど現れず、存在感が薄れてしまいます。ユーザーは長期間更新のないアカウントをフォローし続けませんし、アルゴリズム的にもエンゲージメントが低下すると投稿が表示されにくくなります。その結果、せっかくフォローしてくれた見込み客との接点を失い、競合他社に埋もれてしまう可能性があります。
一方、投稿が多すぎる場合も注意が必要です。ユーザーのタイムラインが自社投稿で埋め尽くされると「押し付けがましい」と感じられ、フォローを外されてしまいかねません。
実際に、「企業アカウントの投稿頻度が多すぎると嫌がられてフォロー解除の原因になる」ことが指摘されています。
ある調査でも、Instagram利用者の30%以上が「投稿回数が多すぎるとフォローをやめる」と回答しています。
さらに投稿過多は1投稿あたりのエンゲージメント率低下を招き、最悪の場合スパムアカウントと見なされて凍結される恐れもあります。
では適切な頻度とはどの程度でしょうか?海外企業のSNS支援企業DowSocialの分析によれば、1日あたりの適切な投稿数は「Twitterで約6回、Facebookで2回、Instagramで3回」が目安とされています。
もちろん業種やフォロワー属性によって最適頻度は異なりますが、「投稿頻度を増やすこと」は多くの企業がフォロワー数増加の施策として挙げる重要ポイントです。
逆に言えば、頻度の極端な偏りは避け、ユーザーに程よいペースで情報提供することが大切です。
2. ターゲット層を理解せずに投稿している
SNS運用でやりがちな失敗が、誰に向けて発信しているのか不明確なまま投稿してしまうことです。例えば商品のPR投稿ばかりしていて、肝心のターゲットユーザーの興味やニーズとかけ離れていれば、いくら投稿しても響きません。ターゲット層の年齢・性別・関心事ごとに、効果的なSNSやコンテンツの形式は異なります。にもかかわらず、こうした戦略設計をせずに闇雲に発信すると「誰にも届かない内容」になりがちです。
実際、「ターゲットを設定しないと誰にも届かないコンテンツが生まれ、コストの無駄になる」可能性が指摘されています。
ターゲット理解不足の具体例として、KIRINが2020年にInstagramで実施したキャンペーンが挙げられます。KIRINは「#私らしいエシカル」というハッシュタグをつけて投稿すると抽選でプレゼントが当たる企画を行いましたが、このキャンペーンは盛り上がりに欠けました。
要因の一つは「エシカル(ethical)」という専門的で馴染みの薄い言葉を使ってしまったことです。「エシカル」の意味を日常的に理解・使用しているユーザーはごくわずかであり、難しいテーマに感じられたため参加のハードルが上がってしまいました。その結果、通常のKIRINキャンペーンに比べ投稿数が約30%も減少してしまったのです。
この事例からも、自社が伝えたいキーワードをそのまま使うのではなく、ターゲットが共感・理解できる言葉やテーマ選びが重要だと分かります。
また、SNSごとにユーザー層が異なる点も見逃せません。例えば、若年層向けの商品なのにビジネス色の強いLinkedInばかり運用していたり、逆にシニア層が多いFacebookで若者言葉満載の投稿をしても効果は薄いでしょう。ターゲットごとに適切なプラットフォーム選定や発信内容のトーン&マナーを考慮する必要があります。**「誰に届けたいのか」**を明確にしないままでは、せっかく手間をかけたSNS運用も成果につながりません。
3. 企業アカウントなのに個人的な意見を発信してしまう
企業公式アカウントで担当者の個人的感情や意見をそのまま発信してしまうのも大きなNGです。SNS担当者個人にとっては日常の何気ない一言でも、企業アカウントからの発信になれば受け手はそれを「会社の見解」と捉えます。軽率な投稿が企業イメージを損ね、炎上につながる危険性があります。
実際に、日本でも担当者の誤った投稿により謝罪に追い込まれた事例があります。世界的ファーストフード店では、公式Twitterで担当者が「4.5時間もの無駄な会議に出席した」「給与は増えたものの周りの反感を買うことが増えた気がする」といった業務に関する不満を投稿してしまい、多くのフォロワーに動揺が広がりました。
当然ながらその企業は即座に不適切発言を謝罪する事態に追い込まれています。
また大手ゲーム企業でも、公式Twitterが「増税→消費を絞るしかない→嗜好品終了のお知らせとかワロス。まず削るのは衣食住だろJKww」といった投稿を行い、大きな批判を浴びました。
「嗜好品より生活必需品を削れ」と読める内容にユーザーから非難が殺到し、企業は投稿を速やかに削除して謝罪しましたが、既に内容は拡散しておりブランドイメージに大きなダメージを受けました。
これらは一見極端な例に思えるかもしれませんが、担当者が公私のアカウントを間違えて投稿する「誤爆」*含め、どの企業でも起こり得るリスクです。
企業公式アカウントはその企業の「顔」であり、一担当者の私的感情で動かしてはならないことを肝に銘じる必要があります。
特に政治や宗教など信条に関わる話題や、特定の個人・団体への評価を述べることは厳禁です。投稿前に「それは担当者個人の主張になっていないか?」と見返し、企業アカウントにふさわしい内容か二重チェックする仕組みを設けましょう。
4. 炎上対策をせずに発信してしまう
SNS運用では、最悪の事態(炎上)を想定した対策が欠かせません。ところが「自社に限って大炎上など起きないだろう」と高をくくり、チェック体制を怠るケースがあります。これも大きな間違いです。不特定多数が閲覧し拡散できるSNSでは、些細な投稿が思わぬ角度から批判を浴び、大炎上に発展する可能性があります。
例えば、米マクドナルドが2012年に行った「#McDStories」というキャンペーンでは、本来はハッピーな体験談を集める目的でしたが、
蓋を開けてみると投稿されたのは異物混入や商品の品質に対するクレームなどネガティブな声ばかりでした。
ポジティブなストーリーを期待していた企業側の狙いに反し、ハッシュタグには苦情が殺到しブランドイメージを損ねる結果となってしまったのです。事前に「自社に不満を持つユーザーが声を上げるかもしれない」と予測できていれば避けられた事態かもしれません。このように、ユーザーの反応を楽観視しすぎるのは危険です。
また、日本企業の例では、ある衣料品メーカーがSNS上で「タイツの日」に合わせたキャンペーンを実施しました。女性がタイツを着用したイラストを募集したところ、一部に性的な連想をさせる投稿が含まれてしまい、「企業の公式広告として不適切」と指摘を受け炎上。結局企業は公式に謝罪する事態となりました。
このケースでは投稿ユーザーが生成するコンテンツのチェック不足が問題でしたが、企画段階でリスクを予見し対策を講じていれば防げた可能性があります。
炎上を完全に防ぐことは難しいですが、リスクを最小化する対策は取れます。まず、投稿前に内容を十分精査し、事実の裏付けがない情報は発信しない、賛否が分かれるセンシティブな話題には極力触れないといった基本を徹底することです。
これらは炎上リスクを大幅に下げますし、仮に炎上まで至らずとも「この企業は信頼できない」「価値観がずれている」といったイメージダウンを防ぐ効果があります。
さらに万一炎上が起きてしまった場合に備えて、初期対応のフロー(投稿削除・謝罪文掲載・関係各所への報告など)を社内で決めておくことも重要です。昨今ではSNS監視の専用ツールやサービスも存在し、24時間体制で炎上の兆候をアラート検知する仕組みを導入する企業も増えています。
こうした事前準備を怠らずに運用することで、「火種に気づかず手遅れ」という最悪の事態を避けられるでしょう。
5. 分析をせずに運用を続ける
SNSマーケティングはやりっぱなしにせず分析・改善を繰り返すこと(PDCAサイクル)が成功のカギです。
にもかかわらず、投稿を続けているだけで結果を振り返らないのは大きなNGと言えます。フォロワー数やエンゲージメント率、クリック数など、追うべきKPIを最初に定め、それらの数値を定期的にチェックしていますか?分析をしないままでは、「なぜ反応が良かったのか・悪かったのか」がわからず、運用担当者の勘に頼った施策になってしまいます。これでは再現性がなく、せっかくうまくいった投稿の成功パターンも活かせません。
実際、SNSマーケティングの成果指標は可視化しやすいため、どの数値で何を計測するかを予め決め、それをもとにPDCAを回すことが重要だとされています。
例えばブランディング目的ならリーチ数やエンゲージメント率、集客目的ならサイト流入やコンバージョン数などを見るべきでしょう。その上で、「どの時間帯の投稿が反応が良いか」「どんな内容がシェアされやすいか」などデータを分析し、次の施策に反映します。これを繰り返すことでSNS運用の精度は高まり、無駄なコストを削減できます。
分析を怠ったままでは、的外れな投稿を続けてリソースを浪費する恐れがあります。一方、データに基づいて改善を積み重ねれば、フォロワーとのコミュニケーションが最適化され成果が出やすくなります。たとえばフォロワーを増やしたい企業の47.1%が「投稿頻度を増やす」施策を実施しているという調査結果があります。
これも、自社アカウントの現状分析から「頻度が足りない」と仮説を立てた企業が多いことを示唆しています。闇雲に投稿回数や内容を変えるのではなく、データに裏付けられた仮説検証型の運用に切り替えることが成功への近道です。
成功事例と改善策
上記で挙げたNG行動それぞれについて、日本国内の事例から学べる改善のポイントを紹介します。同じ失敗を乗り越えて成功したケースからヒントを掴みましょう。
- **投稿頻度の改善例:**ある老舗飲食店では、開設当初SNS投稿が月に数回程度と少なく、フォロワーも伸び悩んでいました。そこで運用方針を見直し、毎日ランチタイムとディナー前に1回ずつ投稿するように頻度を増やしたところ、投稿あたりの反応率が向上し、3ヶ月でフォロワー数が2倍に増加しました。
重要なのは単に量を増やすだけでなく、ユーザーが見やすい時間帯にコンスタントに投稿した点です。
これによりユーザーのタイムライン上での露出が増え、エンゲージメントも高まりました。同様に、大手企業の中にはTwitterで1日5〜6回の投稿を維持してファンとの接点を逃さないよう工夫している例もあります。
一方で投稿しすぎによるフォロー外しリスクもあるため、反応データを分析しながら最適な頻度を探っています。
このようにPDCAを回しつつ頻度を調整した企業は、安定した情報発信でユーザーとの関係構築に成功しています。 - ターゲット理解の改善例:洋服の青山を展開する青山商事は、従来のビジネススーツ需要だけでなく10〜20代の女子学生という新たなターゲットに目を向けました。
そのためにInstagram上で「ガールズアカウント」を開設し、若い女性が興味を持つコーディネート紹介や着回し術といったコンテンツを発信したのです。
その結果、従来は接点のなかった女子学生層にリーチしフォロワーを獲得、SNSならではの新規顧客開拓に成功しました。
この事例から学べるのは、ターゲットに合わせて発信内容や運用媒体を大胆に変える戦略です。
また、ファッションセンターしまむらの公式Instagramも、主婦層に向けてコーデ写真を投稿し親しみやすさで成功した例として知られています(手頃な価格の商品を着用したスタッフのリアルなコーデ写真が共感を呼び、フォロワー急増)。
いずれも「誰に届けたいか」を明確にし、その層に響くコンテンツ作りを徹底したことが功を奏しています。 - 企業アカウントの人格設定:先述のように企業アカウントでの個人的発信はNGですが、企業の世界観を壊さない範囲で“人間味”を持たせること自体は有効です。
成功例としてよく挙がるのがシャープ株式会社の公式Twitterです。
シャープの中の人(担当者)はあえてくだけた口調で日常ネタや他社アカウントとの軽妙なやり取りを発信し、それが「親しみやすい企業」として大きな話題になりました。
ポイントは、担当者の個人的信条や企業方針に反する意見は一切出さず、あくまで企業に好意を持ってもらうためのユーモアに徹している点です。
「企業の人となりが分かる何気ない投稿」が多すぎると嫌がられるとの調査もありますが、シャープの場合は内容の節度を守りつつファンとの交流を重ねたため好意的に受け入れられています。
つまり、**個人の暴走ではなく計算された“キャラクター戦略”**として企業アカウントに人間味を与えたことが成功の鍵です。
他社でも、投稿ガイドラインを整備した上でユーモア担当の「中の人」を配置し、ブランドイメージ向上につなげている例があります。
企業の顔として許容できる範囲内で親近感を演出することは、フォロワーとの距離を縮める有効な手段と言えるでしょう。 - 炎上リスク管理の成功例:不適切投稿による炎上を避けるため、事前対策を徹底している企業も増えています。
たとえば、ある大手飲料メーカーでは、Twitterに投稿する全てのコンテンツについて社内チェックフローを二重化しました。
担当者が投稿文と画像を作成した後、広報責任者が「社会的に問題となる表現がないか」「機密情報の漏洩にならないか」「第三者の権利を侵害していないか」など複数の観点で確認してから投稿する仕組みです。また万一炎上した場合に備え、初動対応マニュアルも策定されています。
実際に同社アカウントで軽微な炎上(キャンペーン企画に批判の声)が発生した際も、このマニュアルに沿って速やかに投稿削除と謝罪を行い、担当役員から経緯説明を発信することで大事に至りませんでした。
迅速かつ誠実な対応が奏功し、ユーザーからは「対応が真摯だ」と逆に評価され信頼回復に繋がったのです。
さらに、先述のゲーム企業のケースでも、投稿後すぐに誤りに気づいて削除・謝罪したこと自体は被害拡大を防ぐ上で適切な対応でした(問題はそもそも炎上の火種を投稿してしまったことですが…)。
このように炎上リスクと向き合い備える姿勢が、結果的に企業の危機管理力を示しブランド価値を守ることにつながります。 - 分析重視で成果を出した例:とある地方自治体は、SNSを活用して地域PRを行う中で、投稿ごとの反応を詳細に分析する運用に切り替えました。
栃木県のデジタル戦略チームでは、SNS投稿に対するエンゲージメント率やコメント内容を毎月レポート化し、どの投稿が地域住民や観光客に響いたかを検証しています。
例えばイベント告知の投稿よりも、舞台裏を紹介した投稿の方が「いいね!」が2倍近く多いと分かれば、次月以降は舞台裏コンテンツを増やす、といった具合に施策へ反映させています。
その結果、SNS経由の観光サイトアクセス数が前年同期比で大幅増加する成果を上げました(分析により利用者の関心に沿った情報発信ができたためです)。
また民間企業でも、求人サービス「Indeed Japan」は人気漫画『ワンピース』とコラボしたテレビCM放映後、YouTube公式チャンネルにそのCM動画を長尺版で投稿したところ「もっと見たい!」というユーザーを上手く取り込み再生数を伸ばすことに成功しています。
これはテレビ視聴者の反応データを分析し、「ネット上でも話題になる」と見込んですぐさまSNS展開した好例です。
こうしたデータドリブンな運用によって、SNS施策が売上や集客といったKPIの向上に直結した企業も多く存在します。「勘や経験」ではなくエビデンスに基づいてSNSを最適化したことが成功のポイントです。
まとめ
SNS運用では「何をどう発信するか」だけでなく、「誰に・いつ・どのように発信し、どう改善するか」まで考える必要があります。今回取り上げたNG行動5つは、裏を返せばSNSマーケティング成功のための教訓と言えるでしょう。すなわち、適切な頻度で存在感を維持し、明確なターゲットに響く内容を届け、企業の顔として一貫性ある発信を行い、リスクに目を光らせつつ、データに基づいて運用を改善することが肝要です。
SNSはうまく活用すれば低コストで顧客との信頼関係を築き、ブランドファンを増やす強力なツールになります。逆に誤った使い方をすれば炎上や機会損失で大きな痛手を被りかねません。本記事の内容を踏まえ、ぜひ自社のSNS運用を振り返ってみてください。小さな改善の積み重ねがやがて大きな成果となります。正しいSNS運用のポイントを押さえ、今後のマーケティング戦略に活かしていきましょう。各種成功事例が示すように、ポイントを抑えたSNS活用で皆さんの事業がさらなる発展を遂げることを願っています。